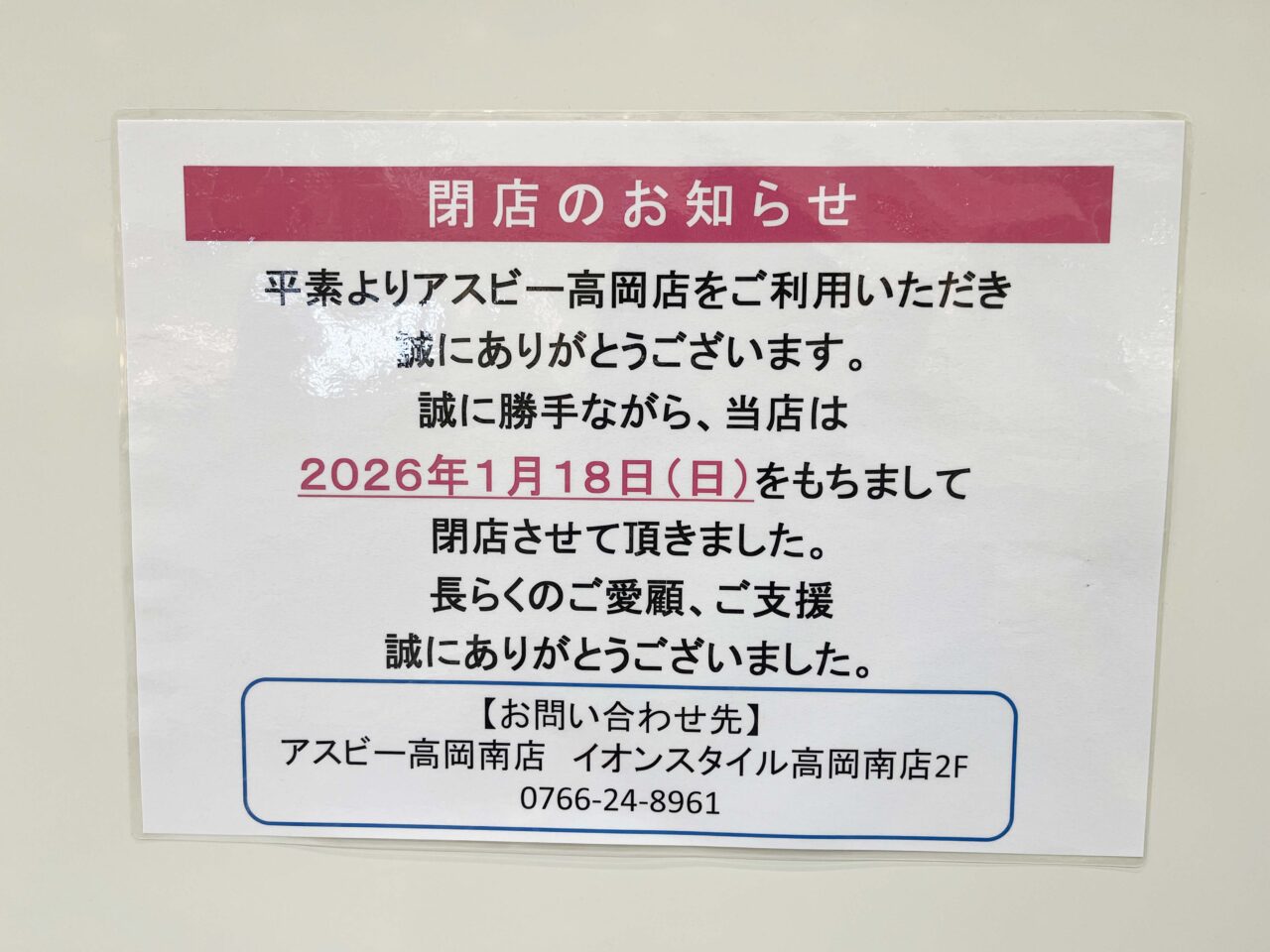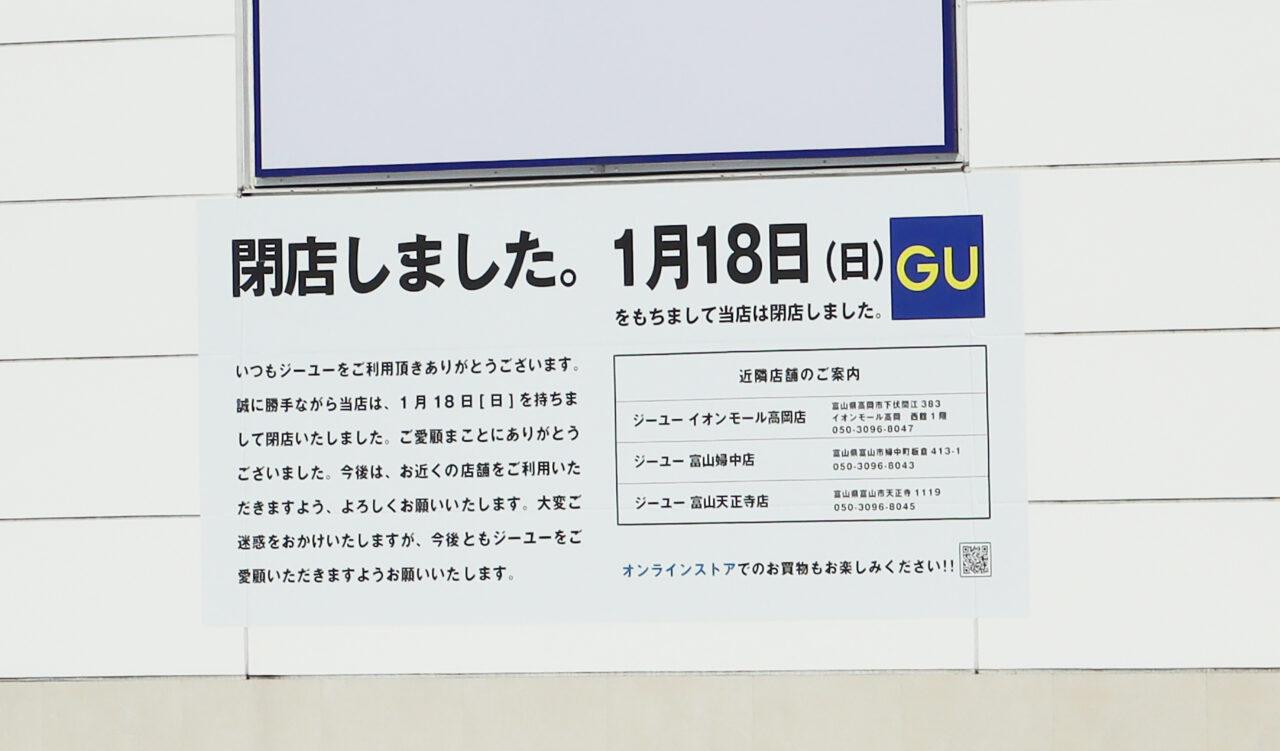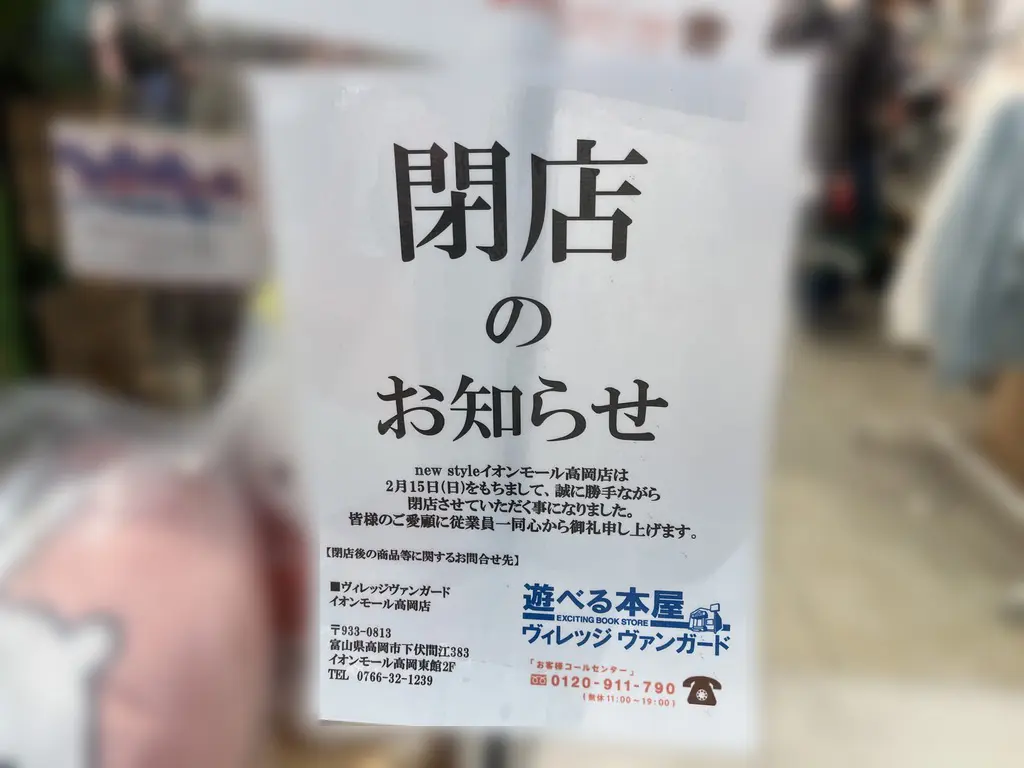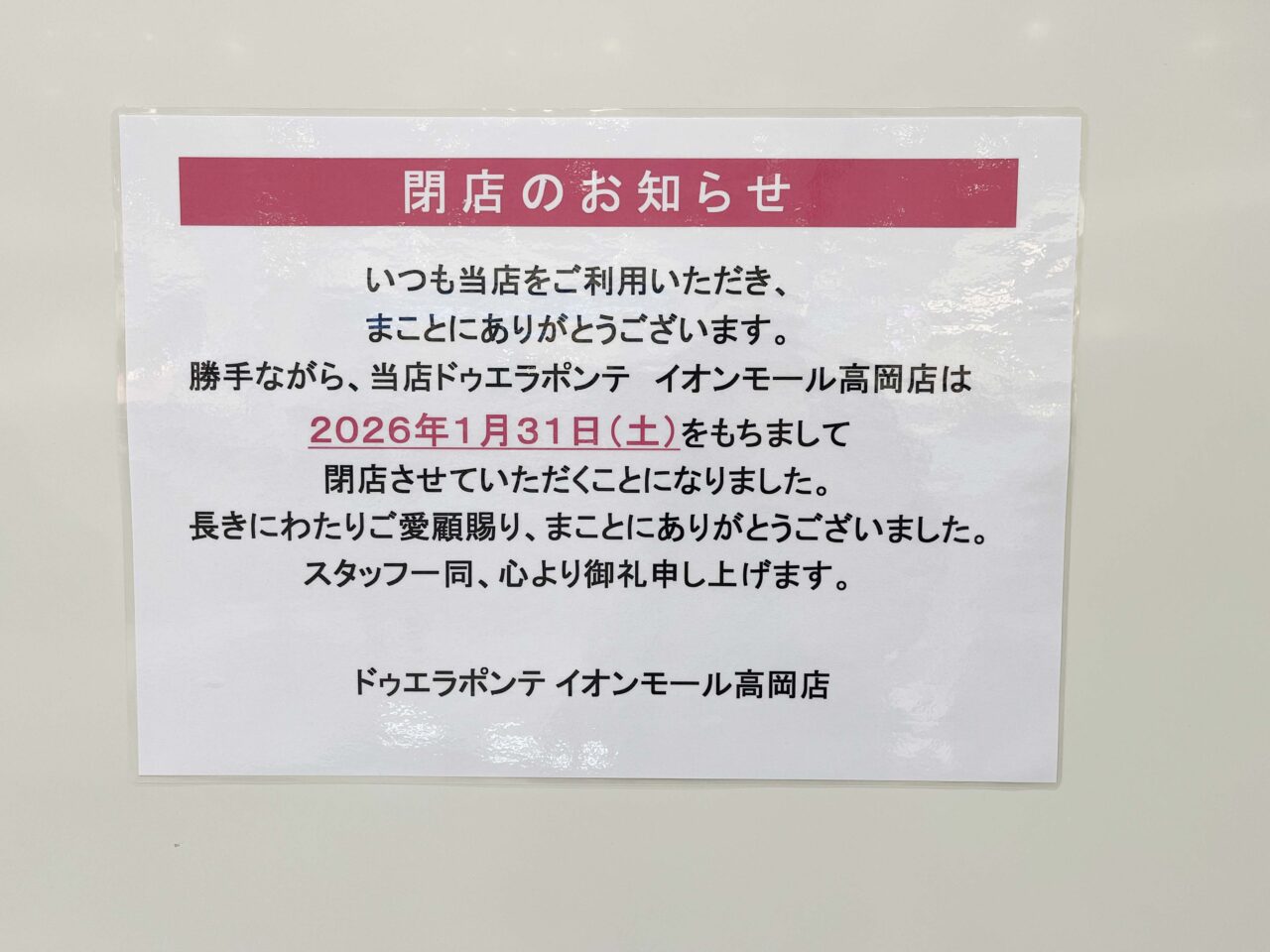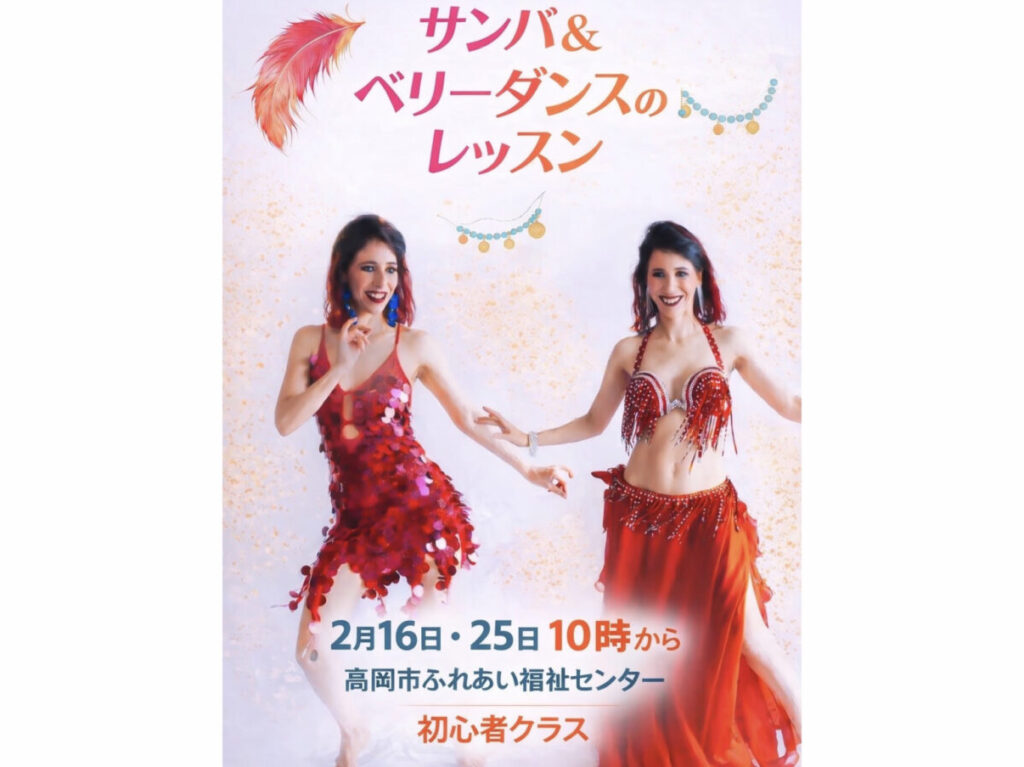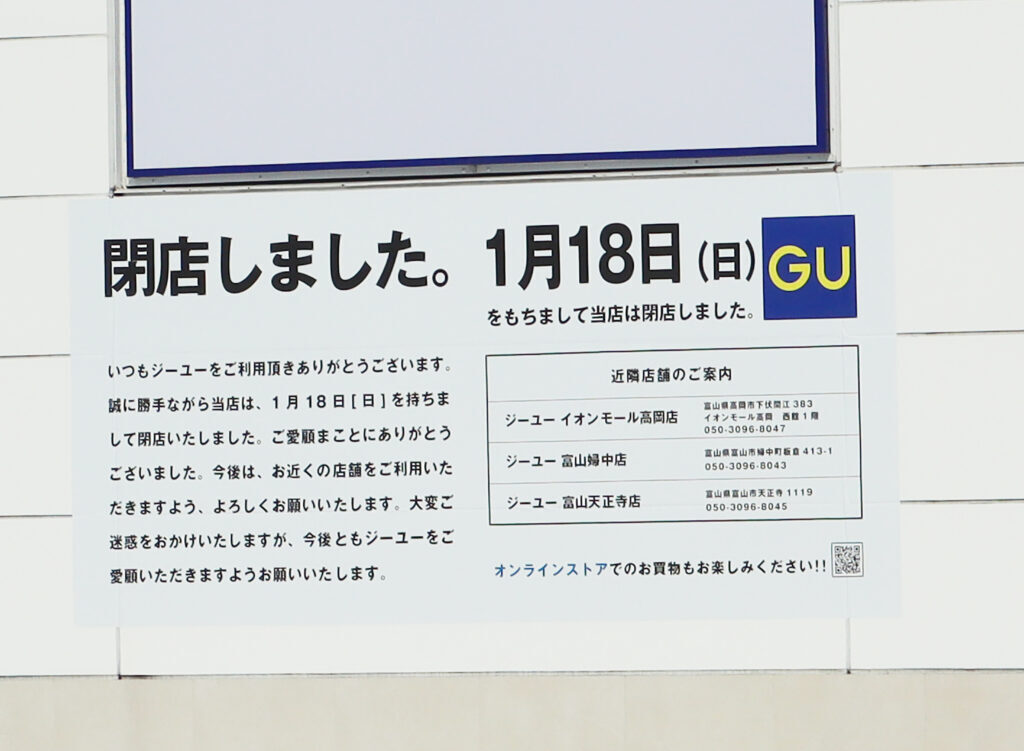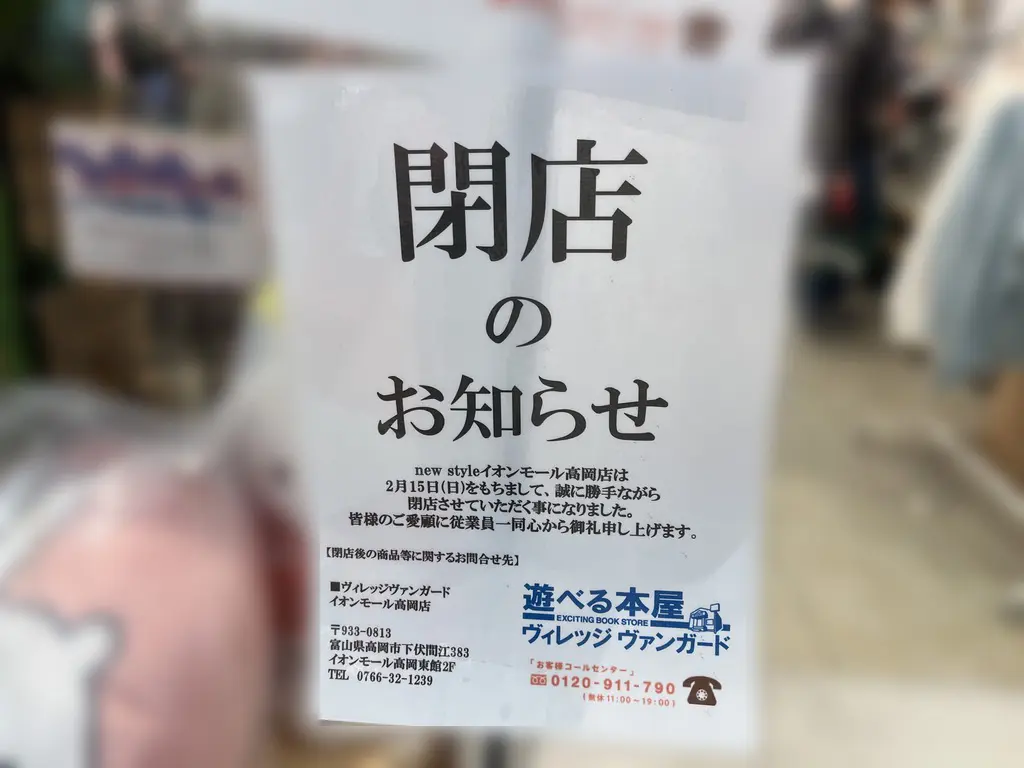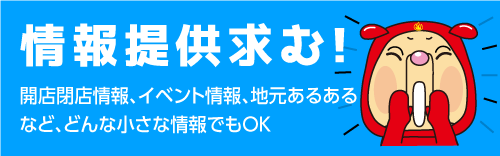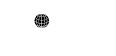【高岡市】瀬川県議に聞く富山の高校再編 時代に、生徒に合った学校づくりを目指して
「生徒が求める学校づくりを」 高岡市選出の瀬川侑希県議に聞く
少子化の進行で県内の高校生が減少する中、高岡市選出の瀬川侑希県議は、富山県立高校の再編について「これからは生徒が求める学校づくりが大切だ」と語ります。従来の数合わせの閉校ではなく、教育の中身や生徒一人ひとりの学びを重視した再編の必要性を訴えています。

瀬川侑希県議会議員
「数合わせ」から「教育の中身」へ
少子化の波が、富山の高校教育にも大きな影を落としています。ピーク時には1学年約1万9千人いた高校生は、今ではその半分ほどに減少しました。県はこれまで平成22年と令和2年の2度、県立高校の閉校·統合を進めてきました。しかし、その多くは「どこかをなくして数を合わせる」ことが目的だったといわれます。
「次はそうではいけない」。そう語るのは、県議会議員の瀬川侑希さんです。瀬川県議は「変化の見通せない時代になった、生徒から本当に求められる学校づくりが大切」だと強調し、教育そのものを見直す必要性を訴えています。
甲子園代表「富山みらい学園」が投げかけた問い
今夏の甲子園で県代表となったのは、通信制高校のサポート校「富山みらい学園」でした。生徒の多くは野球に打ち込むために県外から進学。吹奏楽部もなく、従来の「県代表」のイメージとは大きく異なる学校でした。
当初は様々な声が上がりましたが、その一方で他校からの応援や吹奏楽部の参加、魚津市の経済界による支援が集まりました。瀬川県議は「県民の高校観が変わった瞬間だった」と振り返ります。

高校再編を考えるWS開催時の様子
得意を伸ばし、自分に合った方法を選ぶ
教育のあり方も変わりつつあります。「5教科が大事」とされてきましたが、今は得意分野をどう伸ばすかも重視されます。大学入試も変化しており、全国ではすでに入学者の半数が総合型選抜(旧AO入試)を利用しています。
「自分が何をしたいのか、何が得意で、どうなりたいのか。自分をよく知ることが大学入試により求められている。高校教育はそれを促す中身になったらいい。例えば、自分でもっと授業を選べるようにしたり。」と瀬川県議。富山県では依然として共通試験が主流ですが、「どちらが良い悪いではなく、自分に合った方法を選ぶことが大切。」と話します。
多様な高校の形を残すために
県教育委員会は現在34校ある県立高校を20校程度に再編する方針を示しています。一方、自民党会派としては25校前後が望ましいとしています。瀬川県議は「これまでのように小規模校をまとめて大規模校にするだけでは不十分。大規模·中規模·小規模をバランスよく残し、それぞれの生徒に合った選択肢を用意するべき。」と強調します。
また、学習だけでなく地域活動やアルバイトなどを通じ、地域と関わる機会を持たせる学校の存在も必要だといいます。「地域の課題や人と触れることが、勉強する理由を見つけるきっかけになる。」との考えです。

高校再編を考えるWS開催時の様子
半年で方向性を
「いい部分は残しつつ、でも知識詰め込みではなく、難しい時代を生徒がたくましく生き抜いていけるよう、富山県教育は変わっていかないといけない。半年ほどで方向性を固めたい。そのために力を尽くしたい。」と語る瀬川県議。県立高校再編の議論は、単なる統廃合の枠を超え、これからの教育の姿そのものを問う局面を迎えています。

瀬川侑希(せがわ·ゆうき)さんは1984年(昭和59年)生まれ、高岡市選出の富山県議会議員です。現在2期目で、自民党会派に所属しています。県議会では教育警務委員会委員長を務めるほか、地域公共交通対策特別委員会などにも所属し、教育や地域の課題に積極的に取り組んでいます。
大学卒業後は企業勤務を経て、地元に戻り政治家に。若い世代の声を県政に届けることを掲げ、子育て支援や教育のあり方、地域振興などをテーマに活動しています。特に教育分野への関心が強く、高校再編や入試制度の変化などについて「時代に合った教育の中身を考えるべき」との立場を示しています。